「〜すべきだ。」「〜して当然だ。」「〜ねばならない。」
などの言葉を口にすることはありますか。
このような考え方を「ねばならぬ主義」または
「べき思考」といいます。
アサーションのところで「アグレッシブ」(攻撃的)な
傾向だった人にこのようなタイプが多いと考えられます。
OKグラムでの基本的構えは「私はOKである。
あなたはOKでない。」物事に批判的で真面目で
厳しいタイプといえます。
このタイプの人は他罰的で要求水準が高く、
自分のことを優先し、他人を軽視したり
無視をする傾向にあります。
「相手が自分の言うことを聞いて当然だ!」
という気持ちに自分の意のままにしたいという
思いが現れています。
これが思い通りにいかない時、
「べき思考」は「どうせ思考」になります。
「どうせ思考」とは
どうせ私なんか・・。」「どうせわかってもらえない・・。」
などに変化します。
「べき思考」や「どうせ思考」などの思い込みを
修正していこうというものがエリスの提唱する
倫理療法なのです。
エリスの理論は
「人間は完璧でない」ことから出発しています。
人間は不完全ですから絶対とか完璧なことは
あり得ないのです。
「べき思考」はこの絶対・完璧を他人にも
要求することになります。
その結果自他ともに不愉快な気持ちになるのです。
このような考えを「非合理的思考」「非倫理的思考」
「非生産的思考」などと呼びます。
これを「合理的思考」にかえていくことで気持ちに
余裕が生まれ、余裕がでてくることによって
表情が変わり、相手に対しても優しくなったり、
協調性のある行動へと変わっていきます。
|
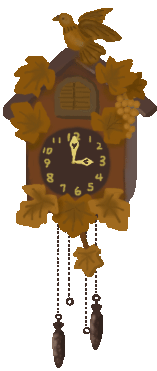
|
エリスのABC理論
A(Adversity)
・・・物事を引きおこす結果となった事柄や事件・言動など
B(Beliefs)
・・・信念・思い込み・特有の習慣や行動
C(Consequences)
・・・・情緒面での結果
D(Dispute)
・・・・論破する。
E(effective new philosophy)
...合理的信念=新しい人生哲学
|
「思考が変われば感情が変わり、感情が変われば行動が変わり、
行動と感情が変れば思考も変わる。」 Albert Elils
つまり悩みを引き起こすような出来事があれば、
その出来事に対してさまざまな症状がでてくると考えるものです。
ただし、それはその出来事を個人がどう受け止めたかによって
変わってきます。
↓
すなわち悩み(C)が起きるには、(A)によって生じたのではなく、
(B)の思い込みの影響で引き起こされているものと考えられます。
↓
従って、(D)の論破で(E)の合理的信念へと導き、
新しい人生哲学を構築しようというものです。
わかりやすい例をあげて考えましょう。
たとえば「仕事で失敗をして上司に叱られて気が滅入っている。」
という場合
「気が滅入っている。」= C(Consequences)は
A(Adversity)=仕事の失敗によって生じたものではなく、
B(Beliefs)=仕事では絶対に失敗は許されない。という
非合理的な思い込みの影響で引き起こされるものである。
そこでB(Beliefs)の思い込みを
D(Dispute)=仕事で失敗する時もあるし、上手くいくこともある。
必ず上手くいくという確証はどこにあるのか。
それは誰が決めたのか。それはどこに書いてあったのか
で論破すると
E(effective new philosophy)=仕事で上手くいくことに
こしたことはないが、今回失敗しても、
別の時には上手くいっているじゃないか。
いつもいつも失敗しているわけではない。
この次は失敗しないようにやればいいじゃないか
という新しい人生哲学が得られるわけです。
エリスはその人なりのものの受け止め方や信念には、
本当に事実や正しい倫理に基づく合理的のものと、
本人が思い込んでいるだけの合理的なものの
2パターンあるとしています。
「〜でなければいけない」「〜べきである」「〜で当然だ」
などのように、要求・命令・絶対的なものの考え方を
非合理的信念といい、これらは選択肢を持たない考え方であり
、事実に基づいていない、倫理的に必然性のないものといい、
合理的信念とは、「できるなら〜するにこしたことはない」
という考え方で、これは現実的で、倫理的であり、
選択肢の余地のあるものといっています。
そこで・・・・
「人は誰からも愛され、誰からも受け入れられなければならない」
これは合理的な考えでしょうか・・。
誰からも愛されたい、いつも愛されていたいという要求は当然のことです。
でもそれが「ねばならない」になるとどうでしょうか。
人には、それぞれ好き嫌いはあります。
それは誰にもあると思います。
誰からも愛されなければいけない。
ということは誰をも愛さなければいけない。
ということでもあります。
それは不可能に近い、非現実的なことです。
つまり非合理的な考えなわけです。
ではこの思い込みを打破するための合理的信念はどうでしょうか。
「人に好かれるにこしたことはないが、
必ずしも好かれるとは限らない。」
「自分のことを嫌いな人がいてもいいじゃないか。」
という新しい人生哲学が自分の中に生まれるわけです。
これは認知行動療法としてカウンセリングの場面で実際使われることもあります。
|